1997年に発売され、今なお世界中のゲームファンから愛され続ける不朽の名作『ファイナルファンタジーVII(FF7)』。
近年ではリメイク作品も大きな話題を呼び、その人気は衰えることを知りません。
しかし、オリジナルのFF7について語られるとき、必ずと言っていいほど話題に上るのが「ポリゴンがひどい」という評価です。
特に、発売当時にプレイしていない若い世代のゲーマーにとっては、カクカクとしたキャラクターモデルに違和感を覚えるかもしれません。
この記事では、なぜFF7のポリゴンが「ひどい」と言われるのか、その理由を当時の時代背景や技術的な側面から深掘りします。
さらに、そうしたグラフィックでありながら、なぜFF7がゲーム史に残る傑作として語り継がれているのか、その魅力の核心に迫ります。
FF7のポリゴンがひどいと言われる理由とは?
鉄アレイと揶揄されたキャラクターモデル
FF7のポリゴンがひどい、と言われる最も象徴的な理由が、フィールドマップ上で操作するキャラクターモデルの独特な造形にあります。
これは、当時のゲーム機の性能限界に起因するものでした。
1997年当時、家庭用ゲーム機で3Dグラフィックをリアルタイムに描画する技術はまだ発展途上であり、使用できるポリゴン(3Dモデルを構成する多角形)の数には厳しい制限がありました。
特に、広大なマップを自由に動き回るRPGでは、キャラクターや背景など、画面内に表示するすべての要素を処理する必要があるため、一つ一つのモデルに割けるポリゴン数は非常に少なくなります。
この制約の中で問題となったのが、キャラクターの「関節」の表現です。
ポリゴン数が少ないモデルで腕や足を曲げると、関節部分のポリゴンが不自然にめり込んだり、尖って見えたりする「ポリゴン割れ」という現象が起きてしまいます。
この問題を回避するため、FF7の開発チームは苦肉の策を講じました。
それが、関節部分(肩、肘、膝など)を球体のように太くし、腕や足の中間部分を極端に細くするというデザインです。
これにより、関節を曲げた際のポリゴンの破綻を目立たなくさせる効果がありました。
しかし、この独特なプロポーションが、まるでトレーニングに使うダンベルや「鉄アレイ」のように見えたことから、後年、インターネット上で「鉄アレイ腕」「ダンベル体型」などと揶揄されるようになったのです。
主人公クラウドをはじめ、ティファやバレットといった主要キャラクターたちがこのモデルで描かれていたため、プレイヤーの印象に強く残りました。
もちろん、これは技術的な制約の中で最善を尽くした結果のデザインデフォルメですが、グラフィックが飛躍的に進化した現代の視点から見ると、その奇妙さが際立ってしまい、「ひどい」という評価に繋がっているのです。
ムービーと通常時で大きく異なるグラフィック
FF7のグラフィックに対する評価を複雑にしているもう一つの要因が、ゲームプレイ中のグラフィックと、イベントシーンで流れるムービーとの間に存在する、あまりにも大きな品質の差です。
このギャップこそが、「通常時のポリゴンがひどい」という印象をより一層強める原因となりました。
この品質差が生まれた理由は、使われている映像技術が根本的に異なるためです。
プリレンダリングムービーの衝撃
FF7の重要なイベントシーンで流れる映像は、「プリレンダリングムービー」という手法で作られています。
これは、PlayStation本体の描画能力とは無関係に、高性能なコンピュータ(ワークステーション)を使って事前に時間をかけて映像を生成し、それを動画ファイルとしてディスクに収録しておく技術です。
つまり、プレイヤーはゲームをプレイしているのではなく、あらかじめ作られた「映画」を観ている状態になります。
この手法により、当時のPlayStationの性能を遥かに超える、非常に高精細で滑らかなCGムービーを実現できました。
オープニングでミッドガルの全景が映し出されるシーンや、召喚獣が派手なエフェクトと共に登場する場面、そして物語の核心に迫るドラマチックなイベントは、この技術によって描かれ、当時のプレイヤーに強烈な衝撃と感動を与えました。
リアルタイムポリゴンの現実
一方、プレイヤーがキャラクターを実際に操作するフィールド探索や戦闘シーンは、「リアルタイムレンダリング(リアルタイムポリゴン)」で描画されます。
これは、プレイヤーの入力に合わせて、PlayStation本体がその都度、瞬時に3Dグラフィックを計算して画面に表示する技術です。
そのため、グラフィックの品質はPlayStationの性能に直接依存します。
前述の通り、当時のハードウェアには厳しい性能限界があったため、キャラクターはカクカクとしたローポリゴン(少ないポリゴン数)モデルで表現せざるを得ませんでした。
この結果、プレイヤーは「映画のような超美麗ムービー」と「鉄アレイ腕のカクカクポリゴン」とを交互に見せられることになります。
ムービーのクオリティが高ければ高いほど、その直後に表示される通常プレイ画面のポリゴンの粗さが際立ってしまうのです。
この著しい落差が、「ムービーはすごいのに、ポリゴンはひどい」という二面的な評価を生み出す大きな要因となったのです。
SFC後期の美麗なドット絵との比較
FF7のポリゴンが粗く見えてしまった背景には、直前のゲーム世代で主流だった「ドット絵」の表現力が、極めて高いレベルに達していたことも大きく影響しています。
特にFF7を開発したスクウェア(現スクウェア・エニックス)は、スーパーファミコン(SFC)時代にドット絵の芸術性を極めたメーカーでした。
FF7の登場は、ゲームグラフィックが2Dドット絵から3Dポリゴンへと大きく舵を切る、まさに時代の転換点でした。
しかし、多くのプレイヤーはSFCで描かれた「完成された2D表現」に慣れ親しんでいたため、黎明期の「未完成な3D表現」に対して、ある種の戸惑いや物足りなさを感じたのです。
例えば、FF7の前に発売された『ファイナルファンタジーVI(FF6)』や『クロノ・トリガー』といったSFC後期の作品では、ドット絵職人たちの手によって、キャラクターの細やかな表情の変化、滑らかなアニメーション、緻密に描き込まれた背景などが、限られたピクセル数の中で見事に表現されていました。
それはもはや単なる絵ではなく、キャラクターの感情や世界の空気感まで伝える力を持つ「芸術」の域に達していたと言っても過言ではありません。
こうした最高峰のドット絵体験の直後に、FF7のローポリゴンキャラクターに触れたプレイヤーの一部が、「SFCのドット絵の方が綺麗だった」「ポリゴンは無機質で表現が乏しい」と感じてしまうのは、ある意味で自然な反応でした。
もちろん、3Dポリゴンには「奥行き」や「カメラワークの自由度」といった、2Dドット絵にはない大きな可能性があります。
FF7はその可能性の扉を開いた先駆者ですが、新しい技術への移行期には、どうしても旧来の技術の洗練度と比較されてしまう宿命にありました。
完成されたドット絵という「過去の最高傑作」の存在が、相対的にFF7のポリゴンの「粗さ」を際立たせ、「ひどい」という評価に繋がる一因となったのです。
同時代の他の3Dゲームとの技術的な差
FF7が発売された1997年前後は、3Dグラフィック技術が日進月歩で進化していた時代です。
FF7のポリゴンが「ひどい」と評される理由の一つに、同時期にリリースされていた、特に他のジャンルのゲームと比較した際の、見た目上の技術的な差が挙げられます。
純粋なキャラクターモデルの品質という点において、FF7が見劣りして見えたのは事実でした。
この差が顕著だったのが、アーケード(ゲームセンター)で人気を博していた3D対戦格闘ゲームです。
| ゲームタイトル | 稼働/発売年 | プラットフォーム | グラフィックの特徴 |
|---|---|---|---|
| バーチャファイター2 | 1994年 | アーケード | 3D格闘ゲームの金字塔。滑らかな動きを実現。 |
| 鉄拳2 | 1995年 | アーケード | 精細なテクスチャマッピングが特徴。 |
| バーチャファイター3 | 1996年 | アーケード | 高度なモーションと表情変化で業界を驚かせた。 |
| ファイナルファンタジーVII | 1997年 | PlayStation | 広大なRPG。プリレンダムービーとローポリモデルを併用。 |
| パラサイト・イヴ | 1998年 | PlayStation | FF7よりリアルな頭身と精細なモデルを実現。 |
3D格闘ゲームとの比較
セガの『バーチャファイター』シリーズや、ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)の『鉄拳』シリーズは、当時の3Dグラフィックの最先端を走っていました。
特にFF7の発売前年にアーケードで稼働を開始した『バーチャファイター3』は、キャラクターの滑らかな動きや起伏のあるステージなど、その圧倒的なグラフィックで大きな話題を呼びました。
これらの格闘ゲームは、登場するキャラクターが少数で、戦闘ステージも限られた空間です。
そのため、開発リソースをキャラクターモデルのディテールやモーションの滑らかさに集中させることができました。
一方、FF7は数十時間にも及ぶプレイ時間、広大なワールドマップ、多数の街やダンジョン、多彩なキャラクターとモンスターを擁するRPGです。
ゲーム全体の膨大な物量を処理する必要があるため、一つ一つのモデルにかけられるコストには限界がありました。
ジャンルが違うため単純比較はできませんが、ゲームセンターで最先端の3Dグラフィックに触れていたプレイヤーから見れば、FF7のキャラクターモデルが相対的に簡素に見えてしまうのは致し方ないことでした。
PlayStation内の進化
また、同じPlayStationのソフトの中でも、開発ノウハウの蓄積によってグラフィックは急速に進化していきました。
FF7の翌年に発売されたスクウェアの『パラサイト・イヴ』や、さらにその翌年の『ファイナルファンタジーVIII』では、キャラクターがよりリアルな頭身になり、ポリゴンモデルも格段に精細になっています。
後発のゲームと比較されることで、FF7のポリゴンが「古い」「粗い」という印象を持たれてしまう側面もあったのです。
FF7のポリゴンはひどい、それでも名作なのはなぜ?
3D技術黎明期における段階的な進化
FF7のポリゴンが「ひどい」と評されることがある一方で、この作品がゲーム史における金字塔であることは揺るぎない事実です。
その理由を理解するためには、FF7を単体のグラフィックとして見るのではなく、3Dゲーム開発の歴史における「重要な一歩」として捉える必要があります。
FF7は、2D表現が主流だったRPGの世界に、本格的な3Dグラフィックを持ち込んだ革命的な作品でした。
それは、開発を手がけたスクウェアにとっても、PlayStationという新しいハードにおける未知への挑戦でした。
開発チームは、3D空間の設計、カメラワーク、キャラクターモデリング、モーションなど、あらゆるノウハウをゼロに近い状態から手探りで蓄積していきました。
その試行錯誤の結晶が、FF7のグラフィックです。
確かに、現代の基準で見れば粗削りな部分は多々あります。
しかし、このFF7という挑戦があったからこそ、スクウェアは3D RPG開発の貴重な経験値を得ることができたのです。
その証拠に、FF7のわずか2年後に同じPlayStationで発売された『ファイナルファンタジーVIII』では、キャラクターモデルの頭身がリアルになり、表情やモーションも格段に進化しました。
さらにその翌年の『ファイナルファンタジーIX』では、デフォルメされつつも温かみのある、完成度の高いポリゴン表現を確立しています。
これは、同じハードウェアであっても、開発者がその性能を最大限に引き出す技術を習得していく過程を示しています。
言わば、FF7は壮大な技術的進化の物語における「第1章」なのです。
FF7のポリゴンは、その後のRPGのグラフィック表現の礎を築いた、かけがえのないマイルストーンです。
その歴史的価値を理解すれば、「ひどい」と一言で切り捨てるのではなく、偉大な進化の序章として、その存在意義を再評価できるのではないでしょうか。
当時革新的だったプリレンダムービーの演出
FF7がプレイヤーの心に深く刻まれた大きな理由の一つに、物語の要所で挿入される「プリレンダリングムービー」の圧倒的な映像美と、その革新的な演出方法があります。
前述の通り、通常プレイ時のリアルタイムポリゴンとの品質差はありましたが、このムービーがもたらす映像体験は、そのギャップを補って余りあるほどの感動と衝撃を当時のプレイヤーに与えました。
スーパーファミコンまでの時代、RPGのイベントシーンは、主にドット絵のキャラクターアニメーションとテキストウィンドウで表現されていました。
それも非常に高いレベルで感情を表現していましたが、FF7はそれを全く新しい次元へと引き上げたのです。
まるで映画を観ているかのような、壮大でダイナミックなCGムービーが、ゲームの物語とシームレスに融合しました。
象徴的なムービー演出
- オープニング: 星空からカメラが降下し、魔晄都市ミッドガルの全景を映し出す。そして、魔晄炉を爆破するために走る列車に乗り込むクラウドへと、視点が滑らかに繋がっていく。この一連のシークエンスは、プレイヤーを瞬時にFF7の世界へ引き込みました。
- 召喚獣: バハムートやナイツオブラウンドといった召喚獣の登場シーンは、もはや単なる攻撃演出ではありませんでした。宇宙から飛来したり、天を裂いて現れたりと、一つ一つが独立した短編映像作品のようなクオリティで描かれ、プレイヤーを魅了しました。
- ストーリーの核心: エアリスが忘らるる都で祈りを捧げるシーンや、セフィロスとの対決など、物語の重要な局面は息をのむような美しい映像で描かれ、キャラクターへの感情移入を極限まで高めました。
ムービーとゲームプレイの融合
さらに画期的だったのは、一部のムービー中にプレイヤーがキャラクターを操作できる演出が取り入れられたことです。
例えば、ジュノンのエレベーターでハイウインドが初登場するムービーシーンでは、背景で壮大な映像が流れながらも、プレイヤーはクラウドを自由に動かすことができました。
これにより、プレイヤーは物語の傍観者ではなく、その世界に実在する当事者であるという感覚を強く抱くことができたのです。
これらの革新的なムービー演出は、FF7の物語をよりドラマチックで忘れがたいものにしました。
通常時のポリゴンがどんなに粗くとも、この感動的な映像体験があったからこそ、FF7は多くの人々の記憶に残る名作となったのです。
一枚絵で描かれた美麗な背景グラフィック
FF7のグラフィックについて語る際、キャラクターモデルのポリゴンに注目が集まりがちですが、世界観の構築においてそれ以上に重要な役割を果たしたのが、驚くほど緻密で美しい「背景」です。
実は、FF7の街やダンジョンの多くは、完全な3D空間ではありません。
その正体は、事前に高精細なCGとして描かれた「一枚絵」なのです。
この一枚絵の上を、プレイヤーが操作する3Dポリゴンのキャラクターが歩き回る、という手法が採用されていました。
これを「プリレンダリングCG背景」と呼びます。
この手法には、当時のハードウェア性能の限界を克服するための、非常に大きなメリットがありました。
プリレンダリング背景の利点
- 圧倒的なディテールと空気感の表現:
背景を一枚の絵として作り込むため、リアルタイムの3Dポリゴンでは到底表現不可能な、細部の描き込みや光と影の繊細な表現が可能になります。これにより、スチームパンク風の魔晄都市ミッドガルの退廃的な雰囲気、古代種の神殿の神秘的な空気、ゴールドソーサーのきらびやかなネオンといった、各ロケーションの持つ独特の世界観を、非常に高いクオリティで描き出すことに成功しました。 - ハードへの負荷軽減:
背景は動かない「絵」であるため、リアルタイムで3D描画する必要がありません。これにより、PlayStation本体の処理能力を、プレイヤーキャラクターやNPC(ノンプレイヤーキャラクター)、エフェクトなどの描画に集中させることができ、ゲーム全体のパフォーマンスを安定させることができました。
プレイヤーは、意識することなくこの美しい絵の中を歩き回り、世界を冒険します。
キャラクターモデルのポリゴンが「ひどい」と感じる一方で、背景の圧倒的な美しさと作り込みに息をのんだプレイヤーは少なくありません。
ある意味で、キャラクターの簡素なモデルと、背景の緻密な一枚絵という、このグラフィック上の「アンバランス」さこそが、FF7ならではの独特な映像表現であり、魅力の一つだったと言えるでしょう。
キャラクターと背景、それぞれの長所を活かしたこの巧みなハイブリッド手法が、FF7の忘れがたい世界観を支えていたのです。
グラフィックを補って余りあるゲームシステム
最終的に、FF7が「ポリゴンがひどい」という評価を乗り越え、不朽の名作として愛され続ける最大の理由は、グラフィックという一面だけでは到底語り尽くせない、革新的で奥深いゲームシステムと、心揺さぶるストーリーにあります。
どれだけ映像が美しくても、ゲームとして面白くなければ、これほど長く語り継がれることはありません。
その中心に位置するのが、FF7を象徴する「マテリアシステム」です。
自由度の高い育成「マテリアシステム」
マテリアとは、魔法や特殊アビリティ、召喚獣などの力が結晶化した球体のことです。
プレイヤーは、このマテリアを武器や防具に存在する「マテリア穴」に装着することで、キャラクターに様々な能力を付与できます。
このシステムの最大の特徴は、その圧倒的な自由度とカスタマイズ性にあります。
- キャラクターの役割が固定されない:
従来のRPGでは、キャラクターごとに「戦士」「魔法使い」といった役割が固定されていることがほとんどでした。しかしFF7では、例えば屈強な戦士タイプのバレットに回復魔法のマテリアを装着すればヒーラーに、魔法が得意なエアリスに物理攻撃を強化するマテリアを付ければアタッカーにと、プレイヤーの思い通りにキャラクターを育成できます。 - マテリアの組み合わせによる戦略性:
武器や防具には、マテリア穴が連結しているものがあります。この連結穴に特定の組み合わせでマテリアを装着すると、特殊な効果が発動します。例えば、「ぜんたいか」のマテリアと「ファイア」のマテリアを連結させれば、敵全体にファイアを放つ「ファイガ」が使えるようになります。「MPきゅうしゅう」と召喚マテリアを組み合わせれば、強力な召喚魔法を使いつつMPを吸収するといった戦略も可能です。この無数の組み合わせを試行錯誤する楽しさが、プレイヤーを虜にしました。
このマテリアシステムに加え、星の命運をめぐる壮大なスケールで描かれるストーリー、クラウドの記憶の謎やセフィロスの存在といったプレイヤーを引き込むミステリー、そして今なお人気の高い個性豊かなキャラクターたちが、FF7の骨格を成しています。
さらに、スノーボードやバイクゲーム、チョコボ育成といった豊富なミニゲームも、冒険の合間の素晴らしいスパイスとなっていました。
これらの魅力的な要素が複雑に絡み合い、グラフィックの粗さを補って余りある、唯一無二のゲーム体験を生み出していたのです。
FF7は、まさしく「ゲームはグラフィックだけではない」ということを証明した、偉大な一作と言えるでしょう。
まとめ:FF7のポリゴンはひどい?当時の技術と名作の理由
- FF7のフィールド上のキャラクターは関節部分が太く「鉄アレイ腕」と揶揄された
- これはポリゴン数が少ないモデルの関節破綻を防ぐための技術的工夫であった
- 事前に制作された美麗なムービーと、通常時のグラフィックの品質に大きな差があった
- ムービーの品質が高い分、通常時のポリゴンの粗さが際立って見えた
- FF7以前のSFC後期のドット絵表現が芸術的なレベルに達しており、相対的に粗く見えた
- 同時期のアーケードゲームなどと比較して、キャラクターモデルの品質で見劣りする部分があった
- FF7のポリゴンは3D技術黎明期の過渡期的な表現であり、後の進化の礎となった
- 映画のようなプリレンダムービーの演出は、物語への没入感を飛躍的に高めた
- 背景は緻密な一枚絵で描かれており、独特で美しい世界観を構築した
- 自由度の高い「マテリアシステム」など、革新的なゲーム性が多くのプレイヤーを魅了した
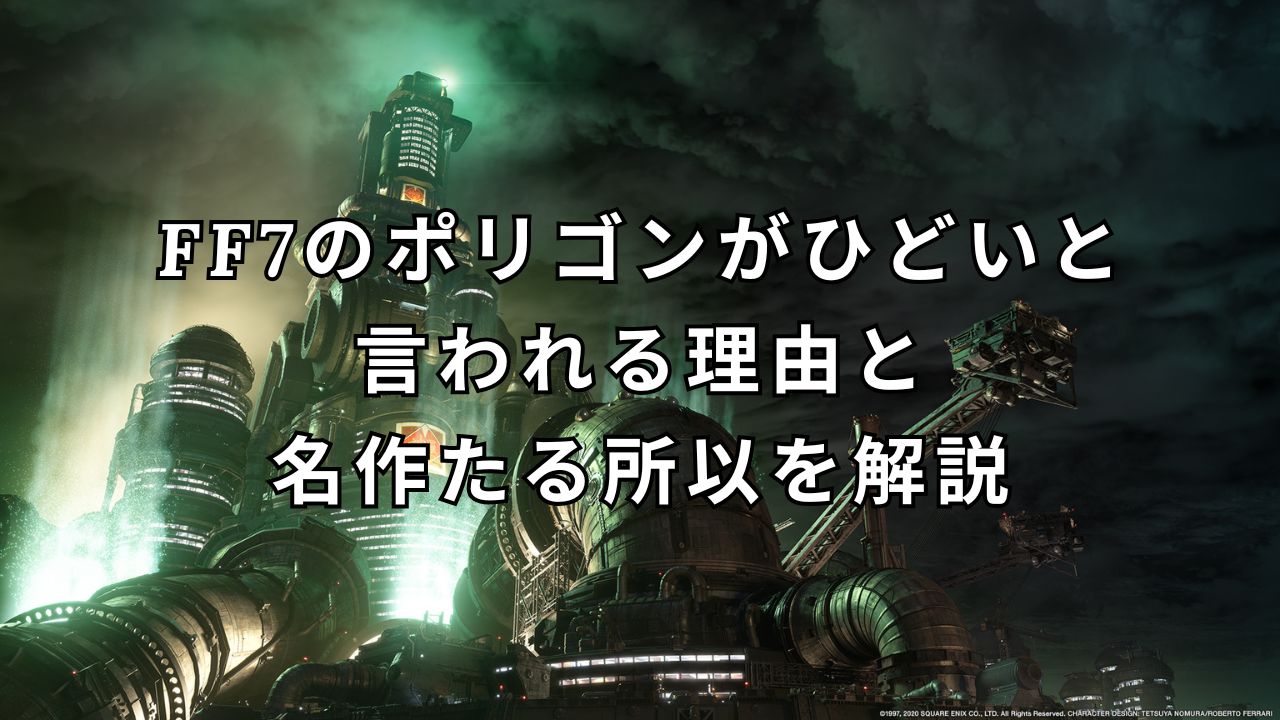
コメント