2024年12月にSteamでリリースされ、瞬く間に話題となったサイコロジカルホラーSF『P.I.』。
ライブ配信をテーマにした独特の世界観と、プレイヤーに委ねられる解釈の広さから、多くのゲーマーがその深い物語の考察に夢中になっています。
この記事では、『P.I.』のストーリーに隠された真相、タイトルの意味、そして散りばめられた謎について、ネタバレを含みながら徹底的に考察していきます。
ゲームをクリアしたけれど謎が残っている、他の人の解釈を知りたい、そんなあなたのための完全ガイドです。
ホラーゲーム『P.I.』とは?ゲームの基本情報とあらすじ

『P.I.』はどんなゲーム?ライブ配信がテーマのサイコロジカルホラー
『P.I.』は、2024年12月26日にSteamでリリースされた、ライブ配信をテーマにした一人称視点のサイコロジカルホラーSFゲームです。
プレイヤーは女性ストリーマーとなり、自宅からライブ配信を行いますが、その中で起こる不可解な現象や徐々に変化していく部屋の様子から、言い知れぬ恐怖を体験します。
敵が直接的に襲ってくるようなホラーではなく、じわじわと精神を追い詰めるような雰囲気や緊張感に焦点を当てた作品と言えるでしょう。
ゲームのあらすじ:配信者連続殺人事件と謎に満ちた部屋
物語の主人公は、パートナーの帰りを待ちながらライブ配信を始める一人のストリーマーです。
世間では「配信者連続殺人事件」が話題になっており、彼女は身元が特定されないよう注意を払いながら、自身の部屋を紹介していきます。
しかし、配信が進むにつれて部屋には異変が現れ始めます。
血の付いた包丁や大きなゴミ袋といった物騒なアイテム、その一方で全く生活感のないパートナーの部屋など、不穏な要素が次々と見つかり、プレイヤーに「この部屋で一体何が起こったのか?」という強烈な疑問を投げかけます。
『P.I.』はループもの?ゲームの基本的な流れ
このゲームの大きな特徴は、「ループ構造」にあります。
プレイヤーはライブ配信中に住所が特定されるようなものを映してしまうなど、特定の条件を満たすと何者かに襲撃され、意識を失います。
そして、再び同じ一日の始まりからゲームが再開されるのです。
この繰り返される一日の中で、プレイヤーは謎を解き明かすヒントを探し、悪夢のようなループからの脱出を目指すことになります。
【ネタバレ注意】ホラーゲーム『P.I.』のストーリー徹底考察
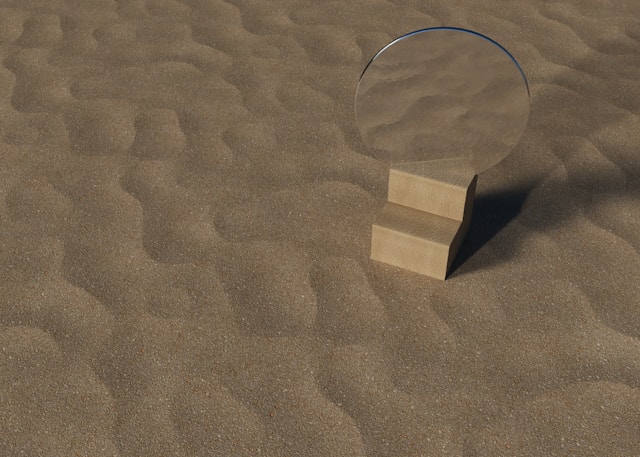
物語の真相は?パートナーの不在と主人公の猟奇的な側面
物語の核心に迫る考察として、パートナーは既にこの世におらず、その原因が主人公自身にあるのではないか、という説が有力です。
ゲーム内で描かれる「まったく生活感のないパートナーの部屋」や、部屋に現れる「血の付いた包丁」といった物証は、この説を強く裏付けています。
主人公が配信を続ける中で徐々に明らかになる猟奇的な側面は、彼女が愛するパートナーを失った喪失感から精神の均衡を崩し、何らかの事件を起こしてしまった可能性を示唆しているのです。
なぜループは起きるのか?「大きな喪失感」が鍵
『P.I.』におけるループ現象は、単なるゲームシステムではなく、主人公の心理状態を表現していると考えられます。
最愛のパートナーを失った「大きな喪失感」と、その事実を受け入れられない罪悪感が、彼女を同じ一日、つまり「事件が起こる前の幸せだった時間」に閉じ込めているのではないでしょうか。
ループを繰り返すたびに部屋の異変が深刻化していくのは、主人公が目を背けている真実に少しずつ向き合わされている過程の現れなのかもしれません。
登場人物の背景と関係性の謎を解き明かす
『P.I.』の登場人物は多くありませんが、その関係性には深い伏線が隠されています。
主人公とパートナーの関係は、彼女の言動から深い愛情があったことが伺えます。
だからこそ、その喪失が彼女に与えた影響は計り知れません。
物語が進むにつれて明らかになる各キャラクターの背景や過去の出来事は、一見無関係に見えても、実は複雑に絡み合っています。
これらの関係性を注意深く観察することが、ゲームの本質を理解する上で非常に重要です。
エンディングの解釈:プレイヤーの選択が結末を変える
このゲームには複数のエンディングが存在し、どの結末が真実なのかはプレイヤーの解釈に委ねられています。
プレイヤーがゲーム内でどのような選択をし、どの情報に注目したかによって、物語の受け取り方は大きく変化します。
あるエンディングでは救いが見出される一方、別のエンディングでは絶望的な結末を迎えることもあります。
それぞれのエンディングに込められたメッセージを読み解き、自分なりの「真相」を見つけ出すことが、『P.I.』という作品を深く味わうための鍵となるでしょう。
『P.I.』のタイトルに隠された意味とは?3つの説を解説

【説1】インタラクティブ(Interactive)の「I」
一つ目の説は、ゲームの紹介ページにも記載されている「インタラクティブフィクション」の頭文字を取ったというものです。
インタラクティブ(Interactive)とは「双方向の」という意味で、プレイヤーの選択や行動によってストーリーが変化する形式の作品を指します。
『P.I.』がまさにこの形式を採用していることから、非常に有力な説と言えます。
【説2】特定する(Identify)の「I」
二つ目の説は、ゲームの重要なテーマである「身元特定」に関連するものです。
英語で「特定する」は “identify” と言い、その頭文字が「I」です。
配信中に個人情報を映してしまい身元が特定される(identifyされる)とバッドエンドに繋がるというゲームシステムは、この説の信憑性を高めています。
【説3】小文字の「l(エル)」と喪失(Loss)の暗示
三つ目は、少し変わった視点の考察です。
ゲームのロゴが小文字の「pi.」で表記されていることに着目し、「I」ではなく小文字の「l(エル)」ではないか、という説です。
これは、物語の根底にあるテーマ「喪失(Loss)」を暗示しているのではないかと考えられます。
愛する人を失った主人公の深い悲しみや喪失感を表現しているとしたら、非常に示唆に富んだ解釈です。
ゲーム内に散りばめられた謎とシンボルの意味を考察
モチーフは名作ホラー『P.T.』?共通点と違いを比較
『P.I.』というタイトルやゲーム性から、多くのプレイヤーが小島秀夫監督による伝説的なホラーゲーム『P.T.』を連想しました。
『P.T.』は “Playable Teaser” の略で、同じ廊下をループしながら謎を解いていくという内容でした。
薄暗い廊下、繰り返されるループ構造、そしてプレイヤーの心理を巧みに突く恐怖演出など、『P.I.』には『P.T.』へのオマージュや影響を強く感じさせる要素が数多く見受けられます。
物騒なアイテム(血の付いた包丁、ゴミ袋)が示すもの
ゲーム中に登場する「血の付いた包丁」や「大きなゴミ袋」は、この部屋で何らかの凄惨な事件が起きたことを直接的に示唆するシンボルです。
これらのアイテムは、主人公が犯した(あるいは巻き込まれた)罪の象徴であり、彼女が目を背けたい記憶そのものと言えるでしょう。
ゴミ袋の中身が具体的に描かれないことも、プレイヤーの恐怖と想像をかき立てる効果的な演出となっています。
文字化けや特定の音、夢のシーンが暗示する真相とは
ゲーム内で時折発生する文字化けや、不気味な音、繰り返される悪夢のようなシーンは、主人公の精神が不安定であり、現実と虚構の境界が曖昧になっていることを表現しています。
関連キーワードにある「pi 考察 文字化け」は、多くのプレイヤーがこの現象に注目している証拠です。
これらは、主人公の抑圧された記憶やトラウマが、現実世界に侵食してきている様子を描写していると考えられます。
「骨」は何を意味するのか?(骨・骨壷・納骨)
「Pi ゲーム 骨」というキーワードは、本作の考察において、単一の意味ではなく複数の重要なシンボルとして扱われています。
第一に、「殺人の証拠」としての「骨」です。
「人間サイズの骨」や「電子レンジの中の骨」は、裕介がこの家で非業の死を遂げたことを示す直接的な証拠として考察されています。
第二に、裕介の死の受容プロセスとしての「納骨」です。
一部の考察では、主人公が裕介の故郷である北海道へ行った理由について、「葬儀や納骨」のためだったのではないかと推測されています。
これは、主人公が裕介の死を現実として受け入れようとするプロセスを描いていた可能性を示しています。
そして第三に、最も重要とされるのが、メタファーとしての「骨壷」です。
特定のエンディングにおいて、白いVRゴーグルとコントローラーを「骨壷」のようなものに入れるシーンが言及されています。
これは、裕介の死の象徴である「骨壷」に、彼が作っていた「VRゲーム(=P.i.という作品そのもの)」を納める(=葬り去る)行為と解釈できます。
つまり、主人公(あるいはプレイヤー)がゲームという虚構の世界と決別し、現実へ戻る(=物語を終わらせる)ことを象徴する、非常に重要なメタファーであると考えられます。
『P.I.』と他の人気ゲームとの関連性は?
『P.T.』(Playable Teaser)との関係性とオマージュ要素
前述の通り、『P.I.』と『P.T.』の関連性は非常に深いものがあります。
単にループ構造が似ているだけでなく、「遊べる予告編」として短いながらも強烈なインパクトを残した『P.T.』のように、『P.I.』もまた、プレイヤーに断片的な情報を与え、物語の全体像を考察させるという手法を取っています。
タイトルロゴの類似性も含め、開発者が『P.T.』に多大なリスペクトを払っていることは間違いないでしょう。
『PSA』というゲームとの違いは?検索で混同されやすい理由
検索の関連キーワードに登場する『PSA』は、深夜放送の放送事故をテーマにしたアナログホラーゲームであり、『P.I.』とは全く異なる作品です。
両者が混同されやすい理由は、おそらくタイトルがアルファベット2文字である点と、共にインディーホラーゲームというジャンルに属しているためでしょう。
『P.I.』がライブ配信を舞台にしたサイコロジカルホラーであるのに対し、『PSA』はテレビ放送というメディアを通した恐怖体験がメインとなっています。
Chilla’s Art作品など他のホラーゲームとの共通テーマ
『P.I.』の考察情報を探すと、YouTuberのマキトchの動画などで、同じく日本の人気インディーホラーゲーム開発チームである「Chilla’s Art(チラズアート)」の作品群が引き合いに出されることがあります。
これは、「日常に潜む恐怖」「日本の住居を舞台にした閉塞感」「心理的に追い詰める演出」といった点で共通項が多いためです。
『P.I.』は、こうした日本のインディーホラーゲームが持つ独特の湿度の高い恐怖の系譜に連なる作品と位置づけることができます。
【ボードゲーム版】推理ゲーム『P.I.』の進め方とルール

ゲームの目的:事件の3要素「犯人」「犯罪」「潜伏場所」を突き止めよ
実は、同名の『P.I.』というボードゲームも存在します。
こちらはホラーゲームではなく、プレイヤーが私立探偵(Private Investigator)となって事件の解決を競う推理ゲームです。
各プレイヤーは、自分の右隣のプレイヤーが担当する事件の「犯人」「犯罪」「潜伏場所」という3つの要素を、誰よりも早く特定することを目指します。
基本的なゲームの流れと3つのアクション
ゲームは3回の「ミニゲーム」で構成されます。
プレイヤーは自分の手番で、以下の3つのアクションから1つを選んで実行します。
- 探偵カウンターの配置:ボード上の特定エリアにカウンターを置き、そのエリアや隣接エリアに事件のヒントがあるか大まかな情報を得る。
- 証拠カードの取得:公開されている証拠カードを1枚取り、それが事件と直接関係があるかどうかの情報を得る。
- 事件の解決を試みる:3つの要素が全て分かったと思ったら、解決を宣言する。
これらのアクションを繰り返し、事件の真相を突き止めていきます。
攻略のポイント:探偵カウンターと証拠カードをどう使うか
このゲームの攻略の鍵は、2種類のアクションから得られる情報の使い分けにあります。
「探偵カウンターの配置」で得られる情報は、「このエリアのどれか」という曖昧なものですが、広い範囲の可能性を絞り込むのに役立ちます。
一方、「証拠カードの取得」で得られる情報は、特定のタイルに直接ヒントが置かれるため、より確度の高い情報となります。
これらの情報をパズルのように組み合わせ、論理的に犯人、犯罪、場所を特定していく過程が、このゲームの醍醐味です。
まとめ:p.i. ゲーム 考察の要点と楽しみ方
- P.I.はライブ配信をテーマにしたサイコロジカルホラーである
- 主人公はループする一日の中でパートナーの帰りを待つ
- 物語の核心にはパートナーの不在と主人公の過去が関わる
- タイトルの「I」には複数の解釈が存在する
- 名作ホラー『P.T.』からの影響が色濃く見られる
- ゲーム内のアイテムやシンボルが物語の真相を暗示する
- 複数のエンディングがありプレイヤーによって解釈が異なる
- 類似名のゲーム『PSA』とは内容が全く異なる
- 同名のボードゲームも存在し、こちらは推理ゲームである
- 物語の謎を解き明かす過程そのものが本作の醍醐味である

コメント